筆者:吉沢一也(スポーツ科学部准教授)
1.私の専門と本学での担当科目
私の専門は古代ギリシアの哲学です。今からおよそ2400年前にギリシアで活躍したソクラテスやプラトンといった哲学者が、当時の社会とのかかわりの中でどのように正義や幸福などについて考えていたのかを中心に研究を進めています。そして、大学では「教養」と呼ばれるいくつかの科目を担当しています。具体的には、基礎的な英語や日本語論作文の授業と、さらに倫理学を担当しています。前者二つは学生が卒業までに必ず単位を取得しなければならない科目であり、後者は興味や関心のある人が選択して履修する科目です。
2.「教養って必要?」という声に向き合う
さて、体育大学を目指す人の中には、「どうして体育大学なのに、専門以外の『教養』を学ぶ必要があるのか?」と疑問を抱く人がいるかもしれません(いて当然です。若者からの似たようなクレームは2400年以上前からありますから)。たしかに実技やトレーニング、専門的な知識を磨くことこそが、競技力の向上や指導者としてのスキルにつながると考えるのは自然なことです。他方、論作文の能力や語学力は、スポーツについて習熟することに即座に役立つようには見えません。しかも今は、AIが文章作成や翻訳をしてくれる時代です。人間が論作文の書き方や外国語を学ぶ意味はないだろうと言う人だっているでしょう(間違いなくいるでしょう。現に大学内で言われることがありますから)。
3.AI時代に教養は必要ない?
ですがこうした意見に対しては、すでに様々な反論が用意されています。たとえば、「将来、何を目指すにしても、理論を的確に説明し、相手に伝えるスキルが不可欠だ。そのためには、論理的に考え、自分の言葉で表現する力が必要になる」とか「AIが作る文章は、表面的には整っていても、論理の一貫性や文脈にふさわしい表現を欠いていることが多い。AIが提供する情報を適切に理解し読み解くには、自分自身で考えて言葉にする力が必要とされる」というような意見です。
4.教養の本質は「もっと知りたい」という気持ち
これはこれでその通りだと思います。しかし一番大切なことは、教養を学ぶということは、単に何かの知識を身につけて終わりというものではないということです。そもそも教養が何を意味するのかは、時代や社会の状況に応じて変化してきました。たとえば、近代においては教養は「市民にふさわしい知識」とされ、現代では「多様な価値観を理解し、柔軟に対応する力」として語られることが多いでしょう。しかし、こうした変化を経てもなお、教養の本質には変わらない部分があります。それは、教養にとって不可欠なのは学びへの志向だということです。平たく言えば、「現状では私の知識は不十分だから、もっと知りたい」と志す姿勢そのものです(ちなみに、古代ギリシアの哲学者ソクラテスの言う「無知の自覚」とはこのことを示唆します)。学ぶ知識の内容は移り変わるものですが、新しい疑問を持ち、問いを立て、考えを深め、よりよく生きるために学び続けることの価値は変わりません。
5.教養は「生涯終わらないトレーニング」
試合が終わったらもうトレーニングしなくていい? そんなはずはありません。競技の技術を維持し向上させるには、日々の鍛錬が欠かせませんよね。試験が終わったら/単位をとったら勉強しなくていい? これにもまた同じことが言えるのです。教養を学ぶということは、何かの知識を身につけて終わりではなく、考え学び続けることそのものです。みなさんには、トレーニングで体を鍛えるように、「もっと知りたい」という気持ちを育んでほしいと思っています。そして私は、教養科目を担当しながら、学生が自ら問いを立て、考え続ける力を育めるような場を提供したいと考えています。



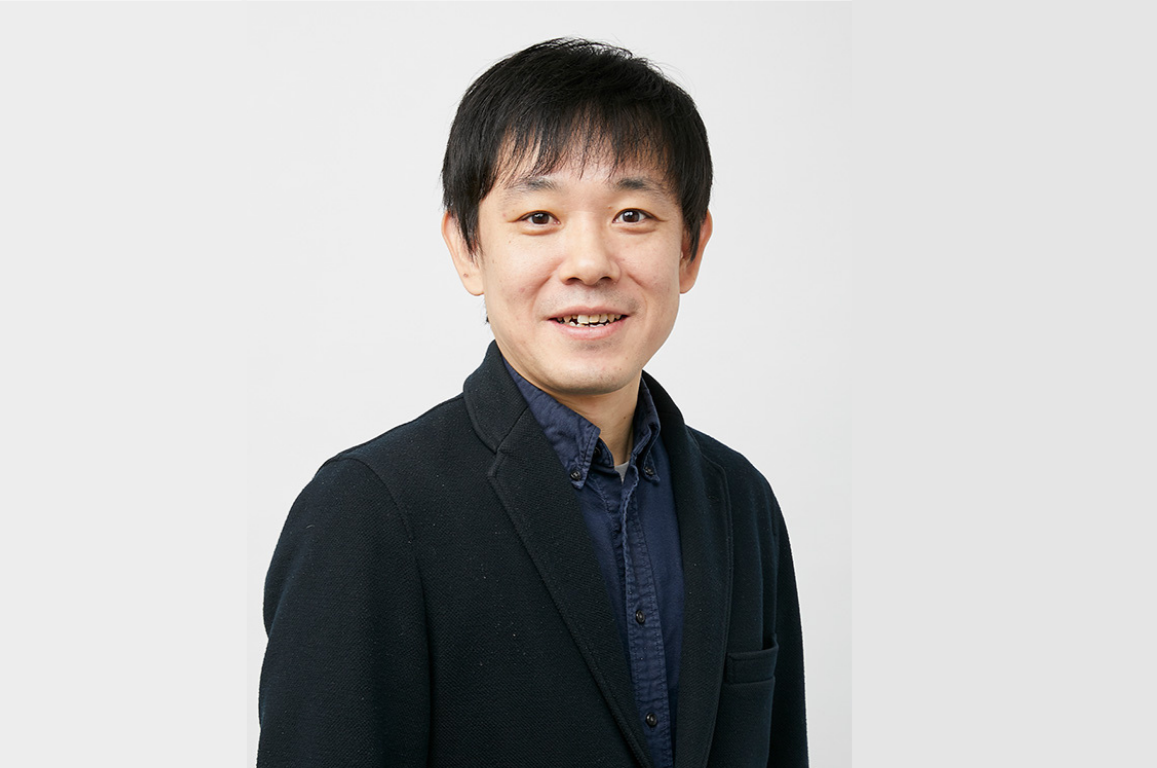

![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK