大阪体育大学の学生が東日本大震災被災地で支援活動にあたる「第18回サンライズキャンプ 被災地復興支援活動in福島」が9月15~18日の3泊4日、福島県南相馬市で実施されました。

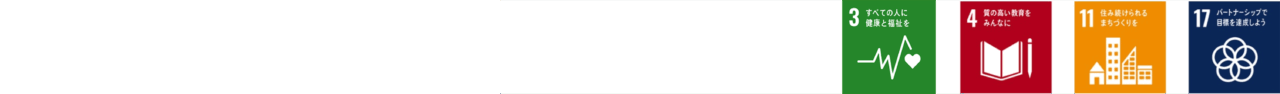
大阪体育大学はスポーツSDGsを推進しています
「サンライズキャンプ」は東日本大震災が起きた2011年の10月、福島県から大阪に避難した子どもたちと学生が大学構内で1泊のキャンプで交流しスタートしました。翌12年はがれきや土砂の撤去が中心でしたが、13年からは地域のNPO法人と連携し、高齢者への体力測定や仮設住宅でのサロン活動、公園など遊ぶ場をなくした子どもたちとのスポーツ交流など、その時のニーズに合わせて内容を少しずつ変えながら、支援活動を継続してきました。学生たちが健康科学、スポーツ指導など大学で学んだ知識を活かし、「体育大学だからこそできる支援」に取り組んでいます。
大阪体育大学社会貢献センターが主催し、今年は応募があった学生16名と、第1回から参加しているスポーツ科学部・池島明子教授(レクリエーション、健康づくり)、中山健教授(スポーツ社会学)ら教職員4名の計20名が参加しました。

一行は仙台空港に到着した後、津波や原発事故の被害などを伝える東日本大震災・原子力災害伝承館や地震・津波の被害の状況がほぼそのまま残る震災遺構の浪江町立請戸小学校などを見学しました。夜は地元のNPO法人「つながっぺ南相馬」元代表の今野由喜さんから、車ごと津波にのみこまれた体験談を聴きました。16日は学生が地域の高齢者の体力、筋肉量、骨密度などを測定してデータを渡し、自宅で手軽にできる健康体操をレクチャーする「お元気度チェック」を実施しました。毎年参加する高齢者も多く、昨年もキャンプに参加して親しくなった学生から「○○さん、この数値が去年より上がっていますよ」と説明を受けるなど交流しました。地域ふれあい交流会で高齢者の方と学生が卓球を楽しんだほか、地元の小学生とはドッジボールを通じて交流しました。また、17、18日は各グループに分かれて、JR小高駅前や近くの工場での草取り、みょうがの栽培施設での収穫などの環境整備活動に取り組みました。
サッカー部・池田翔さん 「地元に帰り復興の先頭に立つ先生に」

サンライズキャンプに初めて参加した体育学部3年、サッカー部男子の池田翔(しょう)さん(学法石川高校)は、キャンプの活動地である福島県南相馬市の出身です。部活動が忙しく、これまで時間を作れませんでしたが、「地元のために恩返しをしたい」と参加しました。南相馬では海辺の方に来たことはなかったといい、「初めて海辺を見た。こんな高くまで水が来て。自分の家には津波がこなかったが、亡くなった人のことを考えると言葉を失った」と振り返りました。
池田さんは6歳の時、被災しました。家は倒壊こそしませんでしたが、中はぐちゃぐちゃになり、原発事故のため避難を命じられ、福島市の親せき宅に一家で約1年間住みました。福島市内の小学校に入学し、いじめにあいました。「みんな、原発のことを知っていた」。「7歳、8歳のぼくにはきつかった」と振り返るほど苦しみました。唯一救ってくれたのが体育の先生。自分に寄り添ってくれ、それで救われたといいます。1年後、避難指示が解除されて南相馬市に戻り、仮設の小学校へ。2年生になって本来の地元の校舎に通うことができたといいます。
サンライズキャンプでは、初日、津波にのまれて九死に一生を得た今野由喜さんの話を聴きました。今野さんは車ごと津波にのまれた時のことを、学生たちに「私は死を経験した」と表現しました。また、生き残った後も食料やガソリンが手に入らず、生きていくために必死だったと語りました。池田さんは「今野さんの体験談は、生きるために必死だった自分たちの経験と合致した」と振り返ります。

また、津波に襲われながらも児童全員と教員が無事で「奇跡の避難」と呼ばれた請戸小学校を見学。東日本大震災・原子力災害伝承館では、自分が小学4年生ごろまで、登下校や学校で必ず胸からぶら下げていた、放射線量を測る「線量計」を久しぶりに見ました。「あのころ、自分たちが経験したことが展示されていた。もっと多くの人に見に来てほしい」と思ったといいます。
サンライズキャンプでは、学生たちが高齢者や子どもとの交流プログラムの準備を整えて臨みました。子どもとドッジボールで交流するプログラムの班長役の学生は、前夜午前2時ごろまで指導案を練ったといいます。池田さんは自分の担当だったサッカー交流は都合で中止になったが、各プログラムで元気よく参加者を盛り上げる役を担いました。
池田さんは福島に戻って保健体育の先生になるのが夢です。ゼミの中尾豊喜教授(学校教育学)から「先生になるなら、ボランティアを通じて地元のことをよく知った方がいい」と助言されました。「福島と言うと、周囲から津波や震災、原発事故のことを言われるが、そのイメージをスポーツの力で変えたい。福島はサッカー、スポーツが盛んな県と言われるように。教員になったらキャンプの経験を活かして、福島の復興に尽くしたい」と力を込めました。










![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK