大阪体育大学体育学部でスポーツ心理・カウンセリングコースに所属する松本優斗さん(4年、大阪・佐野高校)は、ライフセービング部での活動にスポーツ心理学のスキルが役立っているといいます。特に実感するのは、「聞く力」と「伝える力」の大切さです。
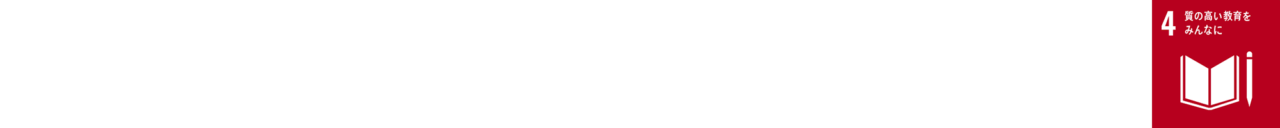

スポーツ心理・カウンセリングコース・松本優斗さん(4年、大阪・佐野高校)
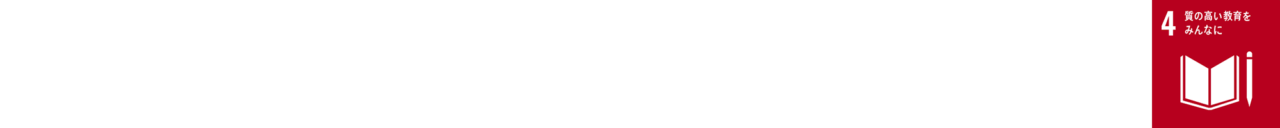
大阪体育大学はスポーツSDGsを推進しています
◆海岸でライフセーバーのリーダーに
松本さんは小中学校でバスケットボール、高校ではダンス部でブレイクダンスに取り組みました。警察官に憧れて大阪体育大学へ。大学では「いろいろな経験を積めるから」とライフセービング部に入部しました。
ライフセービング部はプールや海でのインカレなど各大会を目指すほか、海水浴場でのライフセーバー活動にも取り組みます。松本さんは昨年まで副主将を務め、和歌山市の片男波海岸などでライフセーバーの現場リーダーである警備長も任されました。
◆後輩の言葉を引き出す「聞く力」
副主将として、後輩から相談される機会は多い。松本さんは「自分もそうだったが、後輩は先輩に意見を言いにくい。どれだけ自分が後輩の考えを聞き出せるかが重要」と話します。
参考になったのは、教育カウンセリングⅡの授業で実践したカウンセリング技術。学生同士でペアになり、まず相手の話に傾聴します。うなずきを入れ、あいづちを打ちます。「あ、こういう風に思っているんだね」と相手の話に言い直し、明確化します。授業で得た「聞く力」を駆使して、後輩から意見を引き出しました。
◆助言よりも「一緒に考える」
「伝える力」も重要です。スポーツ心理学を学ぶ前は、相談を受けると、「『ああした方がいい』などと、自分の意見をバンバン伝えていた」といいます。しかし、スポーツ心理学に触れた後は、後輩が思っていることをすべて聞き出し、その後でどう解決したらいいのか、後輩と自分が一緒に考えていく形に変えていったといいます。
◆プレッシャーを感じやすい性格
松本さんがスポーツ心理・カウンセリングコースに進んだのは、過去の苦い経験が理由です。バスケットボールの試合でも、ブレイクダンスのバトル対戦でも、緊張して思うように動けませんでした。プレッシャーを感じやすい点が自分の課題だと思っていたといいます。
◆部の運営にスポーツリーダーシップ論を活かす
ライフセービング部の副部長を務めるうえで心強かったのは、ゼミの先生でもある小菅萌准教授のスポーツリーダーシップ論の授業でした。授業は、「リーダーの役割には、チームを指揮する課題リーダー、雰囲気づくりを担う社会リーダー、目標達成に向けて励ます動機づけリーダー、外部とのコミュニケーションを取り持つ外的リーダーの4つがある」「チームの中の一人が4つのリーダーの役割で最も良いリーダーであると答えた人は、研究では2%」「リーダーシップの役割が分散しているとチームの機能も高まる」という内容です。松本さんは主将と一緒にこの授業を受け、「自分がすべて責任を持たず、得意な部分以外は他の部員にやってもらったらいい」と言い合って、気持ちが楽になりました。部にはスポーツ心理・カウンセリングコース所属の部員が何人かいて、「おれは、こういう役目やな」とリーダーを分けたのは、部を運営するうえで大きかったといいます。
◆法務教官、消防士を目指して
卒業後の進路は、少年院などで非行少年と向き合い社会復帰を支援する法務教官、消防士を目指しています。「法務教官は授業で学んだカウンセリング技術を活かせると思う。また、ライフセービングの活動を通して消防士への関心も高まった」といいます。
◆スポーツ心理学を学ぶメリットとは
スポーツ経験者が心理学を学ぶことのメリットとは。松本さんは「スポーツをしている人には、緊張、失敗、バーンアウト、けがなど誰でも悩みがある。スポーツ心理学の知識があれば、悩んでいる自分にもチームメイトにもアプローチすることができる」と話しています。




![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK