大阪体育大学は、社会貢献センターが中核となって、大学の教員や学生、大学施設を学外の公的機関や組織、企業などと積極的に結びつけ、スポーツの推進や学校教育・支援教育、地域つくりへの貢献を目指しています。社会貢献センターの活動について、センター長のスポーツ科学部・冨山浩三教授(スポーツマネジメント)に聞きました。
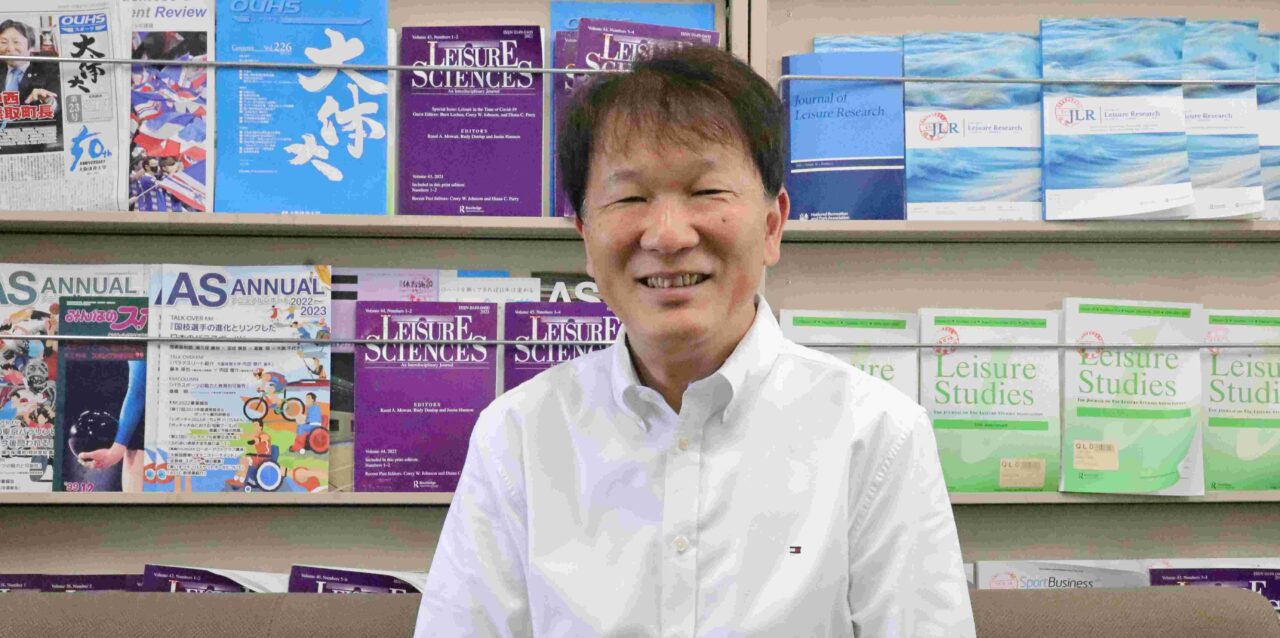
冨山浩三・社会貢献センター長

大阪体育大学はスポーツSDGsを推進しています
――社会貢献センターとは
大学のヒトとモノを社会とつなげ、学生にとって学びの機会、さらには教員の研究成果の発表や研究データの収集の機会を創出することで、社会に貢献する組織です。センターは3部会から成り、「センター事業部会」では、大学として主体的に運営し各教員が企画・実施している事業を統括しています。「地域交流部会」は自治体などから依頼がある社会貢献事業を担当するほか、各クラブがそれぞれ実施している社会貢献イベントも領域としています。「高大連携部会」は高校への出前講義、論文指導など高校との連携事業を扱っています。
――センターが発足した経緯は
大阪体育大学は1965年の開学当時、社会体育、生産体育、学校体育の3分野での人材養成を標榜しました。体育学部では、産業体育研究所が改組されて生涯スポーツ実践研究センターとなり、一方で健康福祉学部の創部に伴い健康福祉実践研究センターも発足し、2018年、一体化して社会貢献センターとなりました。
――主な事業は
以下のリストが主な事業です。
OUHSスポーツキャンプ
福島復興支援サンライズキャンプ
能登半島地震被災地支援
子ども運動教室
子どもスポーツクラブ「キッズボーシャーズ」
障がい体験授業(熊取町全小学校)
特別支援教育教育講演会
特別支援教育トワイライト研修会
ライフスポーツ財団委託研究事業
泉大津市めざせスポーツマスター
泉大津市スノーキャンプ
ウィンターキャンプ(ひとり親家庭の子ども対象)
熊取ちびっこキャンプ
貝塚市立永寿小学校大学見学
出前講座(15校)

――サンライズキャンプとは
東日本大震災が起きた2011年は、福島から関西に避難した子どもたちをキャンパスに招き、キャンプを通じて交流しました。翌年から毎年、学生が被災地に行き、子どもたちとのスポーツを通じた交流、お年寄りの体力測定や健康活動など「体育大学だからこそできる支援」を継続しています。被災地では地域に人がまだ十分には戻らず、小学校も縮小されて震災以前の生活には戻っていません。そういう中で交流することで地域の方の力になればと考えています。また、本学は警察、消防を目指す学生が多く、教員を目指す学生も自分の目で被災地を見て子どもたちに伝えたいという思いでキャンプに参加するケースも多い。ツーリズムの分野では、アウシュビッツ、広島の原爆ドームなど人類の負の遺産を訪れ、厳粛な気持ちでそこで起きたことについて語り部から話を聞き、自分の目で見る「ダークツーリズム」という領域があります。学生たちが福島で何が起きたのかを直接目で見て、自分は何ができるのかを考え、経験し、非常に価値のある学びの場となっています。
――各事業を運営しているスタッフは
例えば、「子ども運動教室」は教育学部の金子勝司学部長が幼小体育研究部の学生とともに実施し、「子どもスポーツクラブ『キッズボーシャーズ』」は体育実技研究部が担当するなど、教員と、その教員が指導するクラブやゼミの学生が中心となっています。他に学生を募集する場合もあります。
――大学が社会貢献活動の取り組むことの意義は
大学は一義的には、社会に役立つ学生を育てて社会に貢献することが必要だが、その過程で、学生は教室で学ぶだけでなく、学外に出て学んだことを社会で実践することが重要です。社会貢献活動を通じて学外の学びの場を学生に提供することは意義が大きい。また、教員は研究の成果を論文として発表するが、論文に書くだけでなく社会実装していく視点が近年では求められている。社会貢献活動が社会実装の場として機能すればいいと思っています。
――社会貢献活動は学生にとってどのような学びにつながっているか
サンライズキャンプに参加して見方が変わった学生は多い。被災地の現状を知ったことをきっかけに、海上保安官になった学生もいます。また、社会貢献活動は活動をしたら終わりではなく、活動を通じてデータを得て分析し、教員の研究はもちろんだが、学部生の卒業論文や大学院生の修士論文にするような場にしたいと思っています。
――今後の課題は
社会貢献センター以外でも、大学全体で行われている社会貢献活動は数多くあります。各クラブもそれぞれ独自に地域交流や子どもたちへの指導を実施しています。まずは活動の全体を集約して、社会に発信していきたい。また、社会貢献センターが教員の研究活動の拠点になり、教員が学生と現地で活動して収集したデータを他の教員が分析するような、領域横断的、学際的な研究につながればと思っています。
<主な事業>
OUHSスポーツキャンプ

地域の子どもたちをキャンパスに招き、スポーツの体験教室を開催。各クラブの学生が指導する
参考記事
子ども運動教室

運動が得意な子も苦手な子、ハンディキャップがある子どもも一緒に運動を楽しむ。幼小体育研究部の学生がスタッフを務める
参考記事
子どもスポーツクラブ「キッズボーシャーズ」

ボール運動やサッカーなどを教員と体育実技研究部の学生が子どもに指導する
参考記事
福島復興支援「サンライズキャンプ」

募集に応じた学生が福島県南相馬市で子どもやお年寄りと交流するほか、東日本大震災・原子力災害伝承館を訪れ、被害の実相を知る
参考記事
ライフスポーツ財団委託研究事業

ライフスポーツ財団の支援を受け、高知県の中山間地域での社会貢献活動、スポーツサミットなど幅広い事業を展開している
参考記事
めざせスポーツマスター

泉大津市から委託された事業で、小学生スポーツ体験プログラム。「泉大津市子ども体力向上プロジェクト」から昨年、移行した
参考記事




![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK