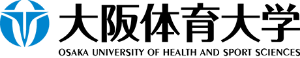筆者:ウエイン ジュリアン(スポーツ科学部教授)
1.国や地域による違い
「ヒト属」が最初に現れた数百万年前から、その多くの種が大地の表面を歩いたことがありますが、現生するのはホモサピエンスだけです。つまり、現在地球上で暮らしている80億人以上の人々は、肌の色や体格等における人種的特徴の違いはあるものの、同じ属に分類されています。なのに、国や地域によってその生活状況に大きなばらつきがあるのはなぜなのか、を疑問に思ったことはありませんか。例えば、日本という「先進国」で暮らしている私たちは、平均として、比較的高い生活水準を享受していると言えますが、多くの人々が生活に苦しんでいる国や地域は少なくありません。また、東欧や中東のように戦争や紛争が頻発する地域もあれば、平和が長く続いてきた地域もあります。このような違いを説明できないでしょうか。
2.文化の違いに「訳」がある
国や地域による違いには数えきれないほどの要素があって、徹底的に説明することは不可能でしょう。しかし、地理学的条件等がこれまでにどのように文明や文化の発達につながってきたのかについて考えると、ヒントが得られることもあります。具体例として、日本とイギリスの違いについて考えてみましょう。ユーラシア大陸に属している島国としてその類似性を強調し比較されることが多くあります。どちらも立憲君主制の多少保守的な国で、例えば謙虚な姿勢を重視する等、似ている文化は確かにあります。しかし、その文化の発達について考えると、大きな違いにすぐに気付きます。比較の対象をここ数百年の歴史にしぼっても、積極的にその版図を広げようとしている大英帝国と外の世界を締め出そうとしている鎖国中の日本の違いは歴然です。この違いにつながった因果関係を探求しても完全な答えにたどり着きませんが、「隔絶度」の影響は考えられます。過去に4回征服されたイギリスは、現代の世界地図では、フランスから30キロぐらいしか離れていないのに対して、第二次世界大戦まで征服されたことがなかった日本の本土は朝鮮半島から200キロ以上離れています。「余計」な影響を抑え日本をより統治しやすくするのに、徳川幕府は隔絶度が高いという特徴をうまく生かしたと言えます。
3.多文化理解の重要性
19世紀後半に、航海技術や軍事技術の進歩を目の当たりにした日本は開国しました。そして、近年の情報技術の目覚ましい発展によって、日本はますます島国としての性質が薄くなってきていると言えます。外の世界を締め出せない現代の日本では、異文化に対して客観的な姿勢を保つことがこれまでになく重要になってきています。一般科目の「文化論」では、文化の違いの「訳」を探ることによって、この姿勢を追い求めています。興味があったら、受けてみてください。

ウエイン ジュリアン(スポーツ科学部教授)
イギリス出身。1994年来日。専門は日本学。担当科目は「文化論」、「総合英語」、「実践英語」、「海外語学研修」。
関連サイト
○ウエイン ジュリアン教授
○大体大先生リレーコラム「本物を学ぼう」